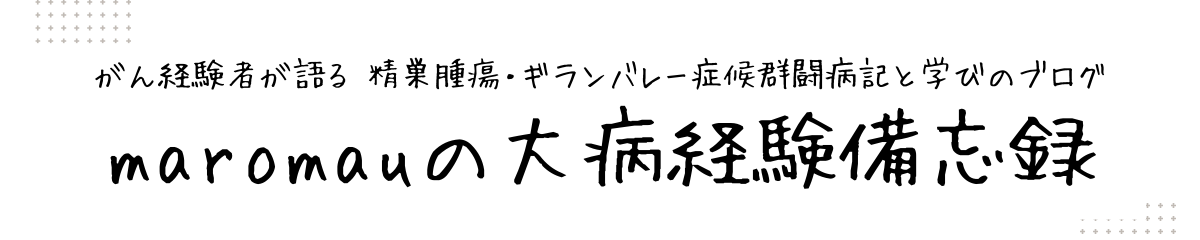精巣腫瘍の手術当日。
22歳の私は、人生で初めて「死ぬかもしれない」という恐怖と真正面から向き合いました。
それでも、支えてくれる人の存在が“生きる力”になった。
あの日の病室、そして手術室でのリアルな体験を綴ります。
手術の朝、ただならぬ緊張感
手術当日の朝。
早朝5時、まだ薄暗い病室で目が覚めました。
体は重く、心臓の鼓動がやけに大きく聞こえます。
「今日、命を懸けるのか」
そう思った瞬間、背中に冷たい汗が流れました。
看護師さんが朝の検温に来て、
「緊張してますか?」と笑顔で聞いてくれました。
私は「はい…ちょっとだけ」と答えましたが、
正直“ちょっと”なんてもんじゃありません。
家族との時間、そして言葉にならない思い
9時前、母が病室に入ってきました。
昨日までとは違う空気。
どちらも何を話せばいいのか分からず、
ただ黙っていました。
母から「頑張ってね」と一言。
その瞬間、涙が溢れそうになりました。
「ありがとう。行ってくる」
父は仕事の関係で来られず、
「絶対大丈夫だから」とメールをくれました。
たった一行のメッセージなのに、
その言葉がどれだけ心強かったか。
手術室までの長い廊下
いよいよ呼び出しの時間。
看護師さんが「準備できましたよ」と声をかけてくれ、
私は病室のベッドに横になったままストレッチャーで運ばれました。
廊下の天井の蛍光灯が、
1本ずつ後ろへ流れていく。
まるでドラマのワンシーンのようで、
「自分が主人公なのか?」という感覚になりました。
手術室の扉が開くと、
一気に空気が変わります。
冷たく、張り詰めた空気。
医療機器の電子音が淡々と一定のリズムを刻んでいました。
麻酔のマスクと、最後の意識
手術台の上に移され、
「お名前、生年月日、手術内容を確認します」
という声が響きました。
間違いなく、私の名前が呼ばれました。
「じゃあ、これから麻酔を入れていきますね。ゆっくり深呼吸してください」
顔にマスクがあてられ、
薬の独特な匂いが鼻を通り抜ける。
「ひとつ…ふたつ…」
心の中で数を数えているうちに、
視界の端がぼやけていく。
そして突如意識がストンと落ちました。
目が覚めた瞬間、感じた『生きている』という奇跡
目を開けた時、
ぼんやりとした光の中で天井が見えました。
そして聞こえたのは、お医者さんの声。
「終わりましたよ。無事に終わりました」
「こんな大きな腫瘍が入ってましたよ」
ホルマリン漬けになった自分のタマを、
まだ意識がはっきりとしないなかで確認。
ひとまず終わったのか・・・生きてる
手術は成功。
左の精巣は無事に摘出されました。
痛みはあったけれど、
心の中ではみなさん“ありがとう”という言葉しかありませんでした。
生きることは、当たり前じゃない
あの日、手術台の上で改めて気づきました。
「生きること」は当たり前ではなく、
多くの人に支えられてこそ続いているということ。
母、父、医療スタッフ、友人、そして彼女。
誰かの存在が、自分を生かしてくれている。
それを《実感》したのが、この日でした。
まとめ:生きる覚悟は、恐怖の先にある
・「怖い」という感情の裏には、必ず「生きたい」という想いがある
・命を預けるとき、人は強くも優しくもなれる
・感謝は生きる力に変わる
手術は人生の大きな節目でした。
でも、終わってみれば「恐怖」よりも「希望」が残っていました。
あの日から、私は少しだけ強くなれた気がします。
医療情報の取り扱いについて
当ブログは筆者個人の体験記です。医療上の判断を目的としたものではありません。症状がある場合や治療の判断は医療機関にご相談ください。記事内で医学的事実・制度等に触れる場合は、公的機関や医療機関、学会等の一次情報を参照し、記事末尾に参考リンクを記載します。
記事の更新・訂正について
制度変更や情報の誤りが判明した場合は、内容を追記・修正し、記事末尾に更新日と修正内容を記載します。内容にお気づきの点がありましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
問い合わせ